なんとか ブログ開設1年 をこえました。これもひとえに、皆様のおかげです。
ご あ ん な い
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
今日は、5時間半という今期最長の試合で疲れました。
それはともかくとして
FMで「オールディーズ」と分類される曲ばかり、
1時間程聞いたんですけど。
やっぱりボクは
「このジャンルの曲は大嫌い!」ですわ。
何で嫌いなのかを自分なりに分析したんですけど、
1)曲自体に思い入れが無い
それは自分勝手な理由やけど、根本に関わる問題ですわな。
2)曲のメロディーが単純
ゆえに「歌」でないと「演奏」では曲の魅力が半減する。
3)オリジナルフォーマットでないとする価値がない。
これ、2)にも通じると思うんですけど、
「悲しき雨音」とか「ハウンドドッグ」なんて、
他にアレンジしようが無い、
言い換えると、他のアレンジでするくらいなら、ほかの曲やれば良い、と。
また、世に「オールディーズ」のファンは多数おられますが、
その殆ど(全部と言っていいかな?)はオリジナルフォーマットでの演奏を期待しています。
ボクの思うスタンダードと呼ばれる曲の最低必要条件は
1)多くの人が知っている曲
2)どんなアレンジをしても成立する
だと思うんですよね。
だから、ボクにとってはオールディーズはスタンダードの仲間には
「絶対」入りません。おそらく永久に。
もちろん、オールディーズが有ったから、
それ以降のポップスやモータウン、AORが出たのはわかるけど…
あ、ビートルズ以降のポップスは(曲によって)スタンダードですよ。
それはともかくとして
FMで「オールディーズ」と分類される曲ばかり、
1時間程聞いたんですけど。
やっぱりボクは
「このジャンルの曲は大嫌い!」ですわ。
何で嫌いなのかを自分なりに分析したんですけど、
1)曲自体に思い入れが無い
それは自分勝手な理由やけど、根本に関わる問題ですわな。
2)曲のメロディーが単純
ゆえに「歌」でないと「演奏」では曲の魅力が半減する。
3)オリジナルフォーマットでないとする価値がない。
これ、2)にも通じると思うんですけど、
「悲しき雨音」とか「ハウンドドッグ」なんて、
他にアレンジしようが無い、
言い換えると、他のアレンジでするくらいなら、ほかの曲やれば良い、と。
また、世に「オールディーズ」のファンは多数おられますが、
その殆ど(全部と言っていいかな?)はオリジナルフォーマットでの演奏を期待しています。
ボクの思うスタンダードと呼ばれる曲の最低必要条件は
1)多くの人が知っている曲
2)どんなアレンジをしても成立する
だと思うんですよね。
だから、ボクにとってはオールディーズはスタンダードの仲間には
「絶対」入りません。おそらく永久に。
もちろん、オールディーズが有ったから、
それ以降のポップスやモータウン、AORが出たのはわかるけど…
あ、ビートルズ以降のポップスは(曲によって)スタンダードですよ。
PR
【ANRI made】 @Mr.ケリーズ
池田杏理(Vo) 今出哲也(P) 西口善之(G/Vo)
やっぱりジャズスタンード一切無し!
無事終了いたしました。
お越し頂いた皆様、有り難うございました。
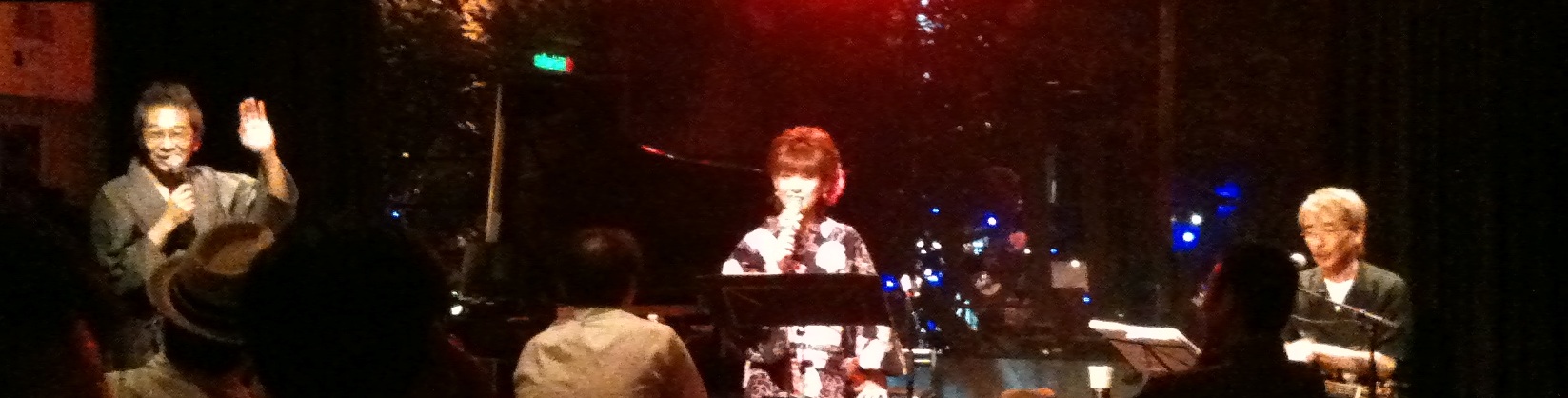
Vocalのお嬢様の浴衣に合わせて、中途半端な和服風のいでたちでおます。
ボクも含め、3人とも「他のメンバーとは絶対にしない(出来ない)」であろう曲がメニューの半分以上を占めておりまして、普段のライブとは違う「疲れ」に襲われております。
近々、HPの方でまたバカみたいに「全曲公開」なんてしますので、暇な方は一度聞いてみて下さい。
で、今回書きたいことはと言うとね。
このグループは、はなから
「ジャズしませ~ん。やりたい曲しかしませ~ん。」というコンセプトで、
演奏する側が自主的に組んだメンバーです。
それゆえ、演奏者サイドでは何ら問題は無い。
問題はねぇ。
お店の方から
「あ、Vocalの○○さんですか?何月何日空いてますか?じゃ、その日、ピアノの○○さん空いてたんで、一緒にお願いしますわ。ベース決まったらまた連絡します」
という、演奏者とは無関係に勝手に決まられるヤツ。
ま、そりゃ一応プロと名の付くプレイヤーが集まれば、
一応の水準の演奏はできるでしょうけどね。
いくら「ジャズライブハウス」と銘打ってる所でも、
これではいきなり「お仕事」という認識にならざるを得ない、
と、思うんですけどね。
ま、いいか。最近はそんな仕事も殆どかからなくなったし。
でも、演奏者・歌手ともに「グループ」ではなく「個人事業者」で動いている人が大半。
おのずと「当たり障りの無いスタンダードを無難に演奏する」セッション風の演奏ばかりで、グループとしての個性とかサウンドなんて出てくるわけないし。評価はあくまで個人に対して。バンドとしてどうのこうのは無視。
「ジャズの醍醐味はセッションや」
それも一理あるかもしれんけど、それがファンのジャズ離れの原因の1つでっせ。長いソロをダラダラとまとまりもなく、退屈!
「こっちで聞いてたらいい感じやったで」
やってる本人が「やりにくい」って言うてるんやから。普段やりなれた、安心できるメンバーでやらしてあげたらいいやんか。
とはいえ、最近「もしかしてボクの考え方が時代にそぐわないのか?」
とも思えてきてます。
まだ当分はこの考えで頑固にいきますけどね。
池田杏理(Vo) 今出哲也(P) 西口善之(G/Vo)
やっぱりジャズスタンード一切無し!
無事終了いたしました。
お越し頂いた皆様、有り難うございました。
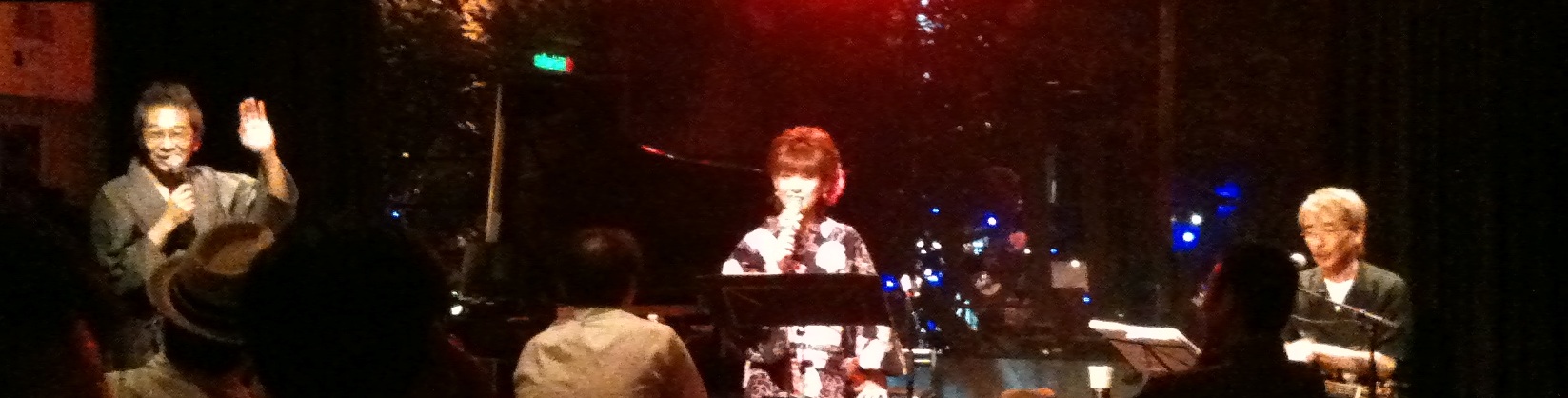
Vocalのお嬢様の浴衣に合わせて、中途半端な和服風のいでたちでおます。
ボクも含め、3人とも「他のメンバーとは絶対にしない(出来ない)」であろう曲がメニューの半分以上を占めておりまして、普段のライブとは違う「疲れ」に襲われております。
近々、HPの方でまたバカみたいに「全曲公開」なんてしますので、暇な方は一度聞いてみて下さい。
で、今回書きたいことはと言うとね。
このグループは、はなから
「ジャズしませ~ん。やりたい曲しかしませ~ん。」というコンセプトで、
演奏する側が自主的に組んだメンバーです。
それゆえ、演奏者サイドでは何ら問題は無い。
問題はねぇ。
お店の方から
「あ、Vocalの○○さんですか?何月何日空いてますか?じゃ、その日、ピアノの○○さん空いてたんで、一緒にお願いしますわ。ベース決まったらまた連絡します」
という、演奏者とは無関係に勝手に決まられるヤツ。
ま、そりゃ一応プロと名の付くプレイヤーが集まれば、
一応の水準の演奏はできるでしょうけどね。
いくら「ジャズライブハウス」と銘打ってる所でも、
これではいきなり「お仕事」という認識にならざるを得ない、
と、思うんですけどね。
ま、いいか。最近はそんな仕事も殆どかからなくなったし。
でも、演奏者・歌手ともに「グループ」ではなく「個人事業者」で動いている人が大半。
おのずと「当たり障りの無いスタンダードを無難に演奏する」セッション風の演奏ばかりで、グループとしての個性とかサウンドなんて出てくるわけないし。評価はあくまで個人に対して。バンドとしてどうのこうのは無視。
「ジャズの醍醐味はセッションや」
それも一理あるかもしれんけど、それがファンのジャズ離れの原因の1つでっせ。長いソロをダラダラとまとまりもなく、退屈!
「こっちで聞いてたらいい感じやったで」
やってる本人が「やりにくい」って言うてるんやから。普段やりなれた、安心できるメンバーでやらしてあげたらいいやんか。
とはいえ、最近「もしかしてボクの考え方が時代にそぐわないのか?」
とも思えてきてます。
まだ当分はこの考えで頑固にいきますけどね。
またいつものコラムみたいな日記でござんス。
若い頃、血気盛んな頃、
「ん~なもん、何が悲しゅてウタバンなんかせなあかんねん!」
とか言ってた頃。
でもラジオから流れる歌は好きだった。
英語があんまり得意でないことも有って、
流れる歌はボクにとっては
「何か言葉を喋ってるように聞こえる楽器の一種」
でした。
メロディーとコードとリズムの絡みさえわかれば充分で、
「そこに意味の有る言葉」は存在理由が無い、と。
だから、日本語の歌は大嫌い。
英語はたまにわかる時が有るからあんまり歌詞は聞かないように。
ポルトガル語なんかはさっぱり何のこっちゃわからん。
だからブラジル音楽が好きだったのかも。
それが歌詞を聞くようになったのは、
意外なことにドリカムから。
NHKの朝ドラのテーマを聞いた近所の人が、
「何歌ってるかわからへん」と言ってはったので、
一回聴いてみると…わからんかった…
通常の我々の会話で使われるイントネーションやら文節
それらを一切無視したようなメロディー。
これじゃ「何歌ってるかわからへん」のも納得と。
じゃ「何歌ってるか、ようわかる」歌は?
と、戦後の歌謡曲ををひもといてみると、
数々のお亡くなりになった名作曲家と言われた方達の歌は
「見事に」会話のリズムで歌になっているではござりませんか。
「韻をふくむ」って、中学校の漢詩でやったよなぁ。
ということに気付くのに10年かかってるし…
「じゃスタンダード、ポップスも?」
と見て行くと…
今までメロディーとコードとリズムの絡みだけでは理解できなかったものが、
歌詞を絡めると「あらま!」簡単に理解できることが数多く…
なんだか随分遠回りしたような気もするけど、まいいか。
最近、Cメロの譜面作る時は、なるべく、歌詞も入れるようにしています。
そういえば、キースジャレットのスタンダードトリオは
リハーサルでメロディーとコードの確認ではなく、
全員で歌詞を確認するとかしないとか。
話を聞いた時は「んなアホな!」と思ったけど、
今なら理解できるなぁ。
でも、日本の歌も、アメリカの歌も、
1950/60/70/80 年頃にくらべてつまんなくなった。
これは散々言われてることやけど。
それを、メロディーとかコードから分析した人はいてるけど、
歌詞の方から分析した人って居てるんやろか?
当時の歌詞は、
「言われただけでときめく」ような、
「歌じゃなければ恥ずかしくて言えない」ような、
「とってもキザな」言い方とか、
そこには「凡人の日常」では無い世界が有りましたわ。
なんせ「プロの作詞家」というものが存在しましたからね。
いまは、ほとんど居ないんじゃないですか?
それゆえ、今の歌詞ときたら、
隣の中学生の日記みたいな文章ばっかり。
だから、「これならオレでも(私でも)できる」とばかりに、
次から次へと…
なかにし礼/戸倉俊一 とか、もう現れないかな。
Richard Rodgers / Oscar Hammerstein II とかも。
というようなことを、
お菓子ポリポリしながら、暑さで仮死状態になって書いてみました。
若い頃、血気盛んな頃、
「ん~なもん、何が悲しゅてウタバンなんかせなあかんねん!」
とか言ってた頃。
でもラジオから流れる歌は好きだった。
英語があんまり得意でないことも有って、
流れる歌はボクにとっては
「何か言葉を喋ってるように聞こえる楽器の一種」
でした。
メロディーとコードとリズムの絡みさえわかれば充分で、
「そこに意味の有る言葉」は存在理由が無い、と。
だから、日本語の歌は大嫌い。
英語はたまにわかる時が有るからあんまり歌詞は聞かないように。
ポルトガル語なんかはさっぱり何のこっちゃわからん。
だからブラジル音楽が好きだったのかも。
それが歌詞を聞くようになったのは、
意外なことにドリカムから。
NHKの朝ドラのテーマを聞いた近所の人が、
「何歌ってるかわからへん」と言ってはったので、
一回聴いてみると…わからんかった…
通常の我々の会話で使われるイントネーションやら文節
それらを一切無視したようなメロディー。
これじゃ「何歌ってるかわからへん」のも納得と。
じゃ「何歌ってるか、ようわかる」歌は?
と、戦後の歌謡曲ををひもといてみると、
数々のお亡くなりになった名作曲家と言われた方達の歌は
「見事に」会話のリズムで歌になっているではござりませんか。
「韻をふくむ」って、中学校の漢詩でやったよなぁ。
ということに気付くのに10年かかってるし…
「じゃスタンダード、ポップスも?」
と見て行くと…
今までメロディーとコードとリズムの絡みだけでは理解できなかったものが、
歌詞を絡めると「あらま!」簡単に理解できることが数多く…
なんだか随分遠回りしたような気もするけど、まいいか。
最近、Cメロの譜面作る時は、なるべく、歌詞も入れるようにしています。
そういえば、キースジャレットのスタンダードトリオは
リハーサルでメロディーとコードの確認ではなく、
全員で歌詞を確認するとかしないとか。
話を聞いた時は「んなアホな!」と思ったけど、
今なら理解できるなぁ。
でも、日本の歌も、アメリカの歌も、
1950/60/70/80 年頃にくらべてつまんなくなった。
これは散々言われてることやけど。
それを、メロディーとかコードから分析した人はいてるけど、
歌詞の方から分析した人って居てるんやろか?
当時の歌詞は、
「言われただけでときめく」ような、
「歌じゃなければ恥ずかしくて言えない」ような、
「とってもキザな」言い方とか、
そこには「凡人の日常」では無い世界が有りましたわ。
なんせ「プロの作詞家」というものが存在しましたからね。
いまは、ほとんど居ないんじゃないですか?
それゆえ、今の歌詞ときたら、
隣の中学生の日記みたいな文章ばっかり。
だから、「これならオレでも(私でも)できる」とばかりに、
次から次へと…
なかにし礼/戸倉俊一 とか、もう現れないかな。
Richard Rodgers / Oscar Hammerstein II とかも。
というようなことを、
お菓子ポリポリしながら、暑さで仮死状態になって書いてみました。

